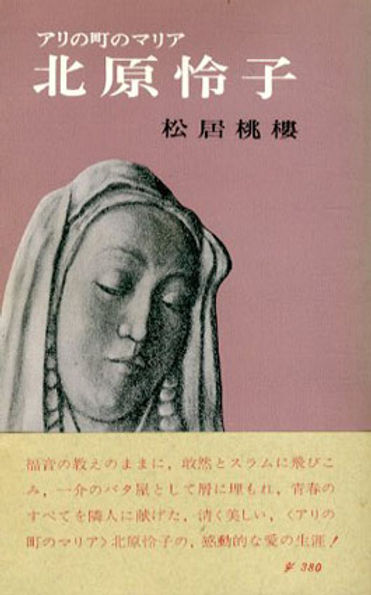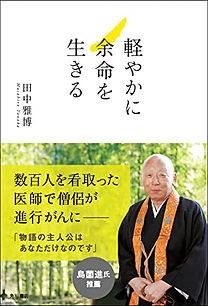柏樹
柏樹社から月間で発行されていた小冊子松居桃楼氏のエッセイは「悪魔学(デモノロジー)入門」として1987年7月から18か月間連載された。このサイトでは、「ト ルストイの予言」という端的なタイトルで、全文を紹介している。
1990年初冬、はじめて水戸のご自宅に伺ったとき、最初にポンと手渡されたのがこの小冊子。黙読する時間を与えてもらったのに、緊張で文字が頭に全然入らず、超後悔。今なら、あれも聞きたい、これも確認したいという思いで一杯。
短編ながら、桃楼おじいさんの思想が、わかりやすい文章で、凝縮されている。
冒頭の「ト ルストイの予言」は必見。
事情を話したら、全巻を無料で謹呈して送っていただいた柏樹社のご担当者様、その節はありがとうございました。

地湧
地湧社から発行されていた小冊子。松居桃楼氏のエッセイは「神の王国は汝らのうちにあり」として1984年7・8月合併号に連載された。このサイトでは、タイトルを「kingdom」と略して、全文を紹介している。
1990年初冬、はじめて水戸のご自宅に伺ったとき、帰るときに手渡されたのがこの小冊子。epilogueにも書いたが……
桃楼おじいさんが、なぜ僕らのようなどこの馬の骨とも分からぬ若造と会ってくれたのか、不思議だった。しかし、その謎がとけたのが、この本を頂いて、家に持ち帰って読んだときだった。
作品後半に登場する、SF漫画のプロットとして描かれていたマンガで世の中を変革しようとする若者たちの話、壊れかけたビルの地下で夢を追う青年たちは、まさに当時の私たちの姿そのものだった。(私たちは古いビルの2階だったのだが)
トルストイの金言を、SF物語のオブラートにくるんで、わかりやすく紹介している。

消えたイスラエル十部族
桃楼おじいさん、一夜の大法螺説法!
「問題の幻の奥義書は、まちがいなく日本に伝わっている」紀元前8世紀、”永遠の生命を得る奥義書”とともに消えてしまったイスラエル十部族。”奥義書”はいずこに? その行方を追求し、歴史の隠された姿を明かし、聖書に秘められた謎、大乗仏典〔法華経〕と古事記の成立の源へ迫る。というのが本の帯の文章。
雪の降るしきる箱根仙石原での一夜、小学生時代からの盟友、中村浩先生との語らいを、テープに記録し、田所静枝さんが文字に起こし、編集したもの。
と簡単に紹介したが、その内容の広さ、深さ、濃さから、製本に至るまでの田所静枝さんのご苦労たるや幾ばくか。
紀元前8世紀から現代までをワープして、万物一如を解き明かすInner space traveler松居桃楼氏の真骨頂を味わえる一冊。

天国ははだか
NHKラジオで、昭和30年代を中心に10数年間、おしゃべりしたものをまとめた本。口語体なのでとても読みやすい。
以下、本の帯のサマリーより
天国はここにある‼
馬鹿になり、裸になれば、天国の門は開ける。狭き門では決してないのだ。知恵とユーモアに満ちた、滋味あふれる人生談話集‼
アダムとエバが、知恵の木の実を食べて、一番最初に感じたことは、恥ずかしいということでした。そこで、神様は、アダムとエバのために、着物を作ってきせてやりました。そのかわり、二人を、エデンの園から追い出した――と、聖書には書いてあります。私は、このことを読んでから考えました。この文章を考えた人は、「人間は、天国へはいりたければ、素っ裸になれ」と言っているのではないだろうか?――と。

はじめはみんな宇宙塵
本当の人間らしさを求めて
「いじめ」の原因はどこに? 桃楼おじいさんが自身の”いじめられっこ”の体験から、弱い者いじめのない世界をめざす人生が始まった。
25年のバタヤ生活で見つけた屑の哲学とは――。弱者へそそぐ桃楼おじいさんの涙が宇宙へと大きく波紋を広げる。
以上、柏樹社の書籍案内より
自分が直接にしろ間接的にしろ、犠牲にしたものの辛さをその身になって感じ心の底からわびたことのない人間が、「弱い者いじめをするな」とか、「核戦争反対」などと、いくら言葉巧みに説教したって、この世の中は少しもいい方へ向かわないばかりでなく、世界の反目、対立はますます激しくなって、いつかは人類撲滅戦争という大破局に突入することを、避けられれない事態を招いてしまうことになるんです。――
以上、本文より

禅の源流をたずねて
NHKラジオ第二放送「宗教の時間」で昭和53年4月から53年3月までの第一日曜日に、12回にわたって放送されたものを、ほとんど手直しせずに、無名庵同人田所静枝さんが書きとったものなので、口語体の文章で、とても読みやすい。
1979年に柏樹社より刊行された本書は、1998年に『微笑む禅 生きる奥義をたずねて』というタイトルで潮文社から甦る。
絶版となっていたことを惜しんだ読者のおひとりが、潮文社社長に掛け合って再出版に至ったという。また、同時に英訳して、アマゾンより「Smiling Zen」として購入可能としたため、いまでは世界中の人が、この本を手にして、読むことができる。
禅が世界的ブームとなる前に書かれたマインドフルネスの決定版。情報の量と質と切り込みの多面性は、他の解説本とは一線を画する。

微笑む禅
元祖マインドフルネス。禅の入門書でありながら、心や人間の奥義までを解き明かす贅沢な一冊。道を求める人にはすべてを与える桃楼おじいさんのご性格がよく表れている。情報の量とクオリティー、そして超刺激炭酸のようなインスパイア力(気づかせ力?)に圧倒される。禅に興味のある方が、最初にこの本に出合ったなら、超ラッキー。
「天才・松居桃楼が生涯をかけてつかみ取ったことを平易に解説してくれています。普通の本は1つでもいいことが書いてあれば「いい本」になれるでしょう。でもこの本にはいろいろなことが凝縮されているのです。絶版になるには惜しい本です。追伸・この本は英訳され、「Smiling Zen」としてアマゾンジャパンで買えます。」




市川左団次
1942年、『市川左団次』として武蔵書房から刊行。記録に残る松居桃楼氏の著作としては最も古く、御年32歳の作品。
市川左団次のバイオグラフィー。当時の出版物としては豪華本で、布製表紙に銀箔文字印刷、箱入りで、本文上下に金の線、写真をふんだんに使用している。
松居桃楼氏のお話では、執筆依頼が来た初っ端から、なぜか、締切りが極端に短かったため、2週間(とおっしゃっていたと思う)、ほとんど不眠不休で、ご本人の視点で書き続け、脱稿時にはバタンキューで倒れてしまったという。
のちに、完成した本を読まれた市川左団次ご本人が、「素晴らしい、本当によく書けている、ありがとう」と言って感謝してくれたため、すべての苦労・疲労が吹っ飛んだとおっしゃっていた。
※ 目次 明治初年の演劇・若き日の悩み・第一回洋行前後・日本の左団次・最後の光・終曲嗚呼市川左団次
昭和16年 330P 非売品

貧乏追放
蟻の街の経済学
1956年『貧乏追放 蟻の街の経済学』として産業経済新聞社・サンケイ新書から刊行される。価格は140円。
読者のみなさまへ
東京浅草の隅田川のほとりに《蟻の街》と呼ばれる奇妙な一角がある。住んでいる人々は一人のこらずバタヤである。
今から7年前、台風に吹きたおされたまま、荒れるにまかせてあった長さ30間の本工場の屋根裏に、裸一貫のバタヤ15人が集まって、「ここを根城に、自分たちの力で起上ろう」と誓い合った。
それから7年、今では住人も150人に増え、100台の大八車、4台のオート三輪が激しく出入りするその入り口には、21寸の大テレビ塔まで立っている。その上、近くの東京湾の八号埋立地に移転し、大一期工費3億5千万円の《新蟻の街》が建設されようとしている。本書は、ここに住む町の学者が、哀歌を織りまぜて綴ったそのルポルタージュである。
以上、本の冒頭(表紙裏)の文章より
いかに世界から貧乏を追放するか、を空論ではなく、蟻の街という現場で臨床的(?)にその問題と格闘している。
どこぞの観念論の人たちにはぜひ《本当の共産主義者》は誰だ?の章を読んでもらい、党名を貧乏追放党でも改めてほしい。彼らがイデオロギーを掲げ続けるせいで貧困問題にフタがされ、日本からいくら経っても貧困層が無くならない。
真の貧困問題解決力のある政党が日本に登場しないかと願っている。

いのちきわみなし
以下、本の帯の文章より
永遠のいのち・法華経の心とは何か?
採光のロマンといわれる法華経そのものを、お年寄りから若者まで、誰でも親しめるよう抜群の構想力により劇画的に説く。現代に生きる生命の秘儀―法華経のこころを探る。
以下、アマゾンレビューより
2018年11月12日
中東を舞台にして展開する物語は、幻想的な世界に導くと共に、宇宙生命に対して多くの教訓を教えてくれる。

蟻の街の奇蹟
1953年、昭和28年1月に国土社から発行された。値段は230円。アマゾンは現在8000円前後で売られている(実際は絶版ゆえに売られていない場合の方が多い)。280ページほどの本なのだが、情報量はハンパない。蟻の街の地図や、自室で虚空を見上げながら執筆中の松居桃楼氏の写真、巻末には警視庁管轄下の浮浪者実態調査表などが載っている。
サブタイトルは「バタヤ部落の生活記録」。ゴミの種類ごとの値段の詳細から子供たちの生活の様、国土社の山口氏との掛け合いまで、松居桃楼さんの独自の視点と孤軍奮闘ぶりはおもしろく、5年後に「蟻の街のマリア」として映画化されることになる、そのエッセンスとヒューモアが、この本に溢れている。
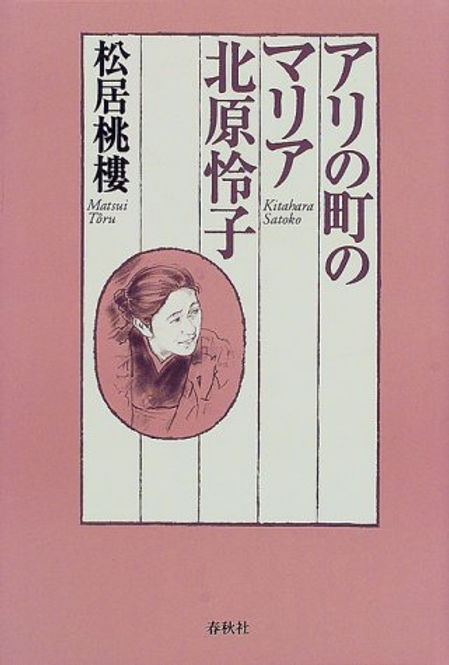
アリの街のマリア
北原怜子
春秋社 1998年版
戦後の貧困と荒廃のなかで、ひたすらの愛だけに生きた29年の生涯。福音の教えのままに、スラム街の一住人となって苦楽を共にし、新天地〈アリの町〉の建設に従事する可憐な北原怜子。
松居桃楼さんは、当初、彼女の霊性が本物かどうかを、わざと厳しい言葉を投げかけて、何度も確かめるが、最後まで北原怜子さんの霊性の輝きは失われることはなかった。
この本を携えてアリの街を訪れた、後に生涯の盟友となる田所静枝さんに、松居桃楼さんは「この本はあなたのために書きました」と言われたそうです。
田所静枝さんと、彼女の後ろに見える大勢の北原怜子さんに向って、桃楼おじいさんはそう言われたのでしょう。
女殺しの桃楼おじいさんです(笑)

ゼノ死ぬひまない
アリの町の神父人生遍歴
「拙い日本語と溢れるほどの無償の愛で、戦後の日本で戦災孤児や被曝者、身寄りのない高齢者に手を差し伸べたポーランド人神父の名前だけは知っていた。その人の歩んだ道は信仰を得る以前から波乱に富んでいた。放浪癖によるのか職を転々とし、ある日、神父になると決意して後のコルベ神父との運命ともいえる出会い。そして、宣教の為に来日した日本で長崎のみならず、日本各地に足を運んだ「聖母の騎士」。「ゼノいそがし、死にひまない」。天に召されて、ゆっくりと休んでいるのだろうか。それとも、また忙しくしているのだろうか」
天台小止観
2014年10月に最も進んだステージのすい臓がんが発見され、余命数か月であることを自覚している医師・僧侶の田中雅博氏による『週刊ポスト』での連載「いのちの苦しみが消える古典のことば」から、天台小止観の「止は禅定、観は知恵」の解釈を田中氏が解説する。
* * *
20年と少し前、天台宗の阿闍梨が、命懸けで、私に止観(仏教のヨーガ)の指導をして下さいました。阿闍梨といっても山の中を歩き続けた方という意味ではありません。「蟻の街」というバタヤ部落(終戦後、廃品回収業に従事する人々が暮らした地区、集落をこう呼んだ)で貧困に苦しむ人々を救うために、苦しむ者と同じ姿に変身する観音菩薩を見倣って、屑拾いとなった松居桃樓師です。
言問橋の袂、東京大空襲後の焼け野原の跡に「蟻の街」ができました。屑拾いで生活し、ときに泥棒をする人もいたようです。泥棒した人を警察署に引き受けに行っていた松居先生は、天台宗の『法華経』でそのような人々を救おうと決心されたそうです。
観音菩薩のように相手と同じ姿になって、一緒に屑拾いをし、必要であれば泥棒もする覚悟をされたのです(fumon.or.jp『蟻の街の奇跡』参照)。その後、蟻の街は見事に自立して、数年後には東京都から埋立地を買い上げて移転しました。
その松居桃樓師は晩年、まさに命が尽きようとするとき、担当医の制止を振りきって救急車で私達の普門院診療所に転院されました。死に場所として観音菩薩の札所である益子の西明寺を選ばれ、住職の私に天台止観の極意を面授して下さったのだと思っています。
蟻の街で松居師を補佐した田所静枝さんが付き添って来られました。彼女は、松居師が『小止観物語』を著された縁で、蟻の街から東京・台東区の寛永寺に通って、二宮守人大僧正の指導のもと『天台小止観』の原文と読み下し文を出版されました。
天台大師の弟子の浄弁が記した『天台小止観』は、中国には不完全なものしか残っておらず、日本の天台宗に伝わっていたものが本来の天台小止観なのだそうです。これを初めて出版したのが静枝さんでした。
「止は禅定、観は知恵」という文は、その『天台小止観』の最初のページにあります。弘法大師空海著『秘密曼荼羅十住心論』では、天台宗の教義は一道無為住心に書かれており、その最後に「奢摩他と毘鉢舍那を修す」とあります。ここで奢摩他は「止」、毘鉢舍那は「観」です。
お釈迦様は、ヨーガの師について先ず奢摩他の達人となり、その後に毘鉢舍那を開拓して「死ぬ」という苦を吹き消しました。松居師も天台小止観解説として『死に勝つまでの三十日』という書籍を著しています。現在、世界中に、特に緩和ケアの現場に、毘鉢舍那が普及し、マインドフルネスと呼ばれています。
松居師を看取った静枝さんも、その後に進行癌となり、普門院診療所に入院され、最後の時を観音経を読まれて過ごされました。松居師と共に、自ら屑拾いとなって蟻の街の生活困窮者たちを救った、法華経観音菩薩の行を確認しながら終末期を過ごされたのだと思います。
* * *
●たなか・まさひろ/1946年、栃木県益子町の西明寺に生まれる。東京慈恵医科大学卒業後、国立がんセンターで研究所室長・病院内科医として勤務。 1990年に西明寺境内に入院・緩和ケアも行なう普門院診療所を建設、内科医、僧侶として患者と向き合う。2014年10月に最も進んだステージのすい臓 がんが発見され、余命数か月と自覚している。
※週刊ポスト2016年12月2日号より
※田中先生の最期のご様子は【NHKスペシャル】「ありのままの最期 末期がんの“看取り医師”死までの450日」で、NHKオンデマンドで視聴可能です

今を微笑む
松居桃楼の世界
溪声社 2014年版
内容説明
戦後、バタヤ集落「蟻の街」を創り支えた桃楼おじいさんからのメッセージ。論考・講演・対談・田所静枝の章などを収録。
目次
第1章 隅田河畔語録
第2章 桃樓「講演」録
第3章 桃樓「対談」録
第4章 随縁自在
第5章 無名庵夢話
第6章 “同志”田所静枝の世界
第7章 追悼=思い出のふたり
第8章 論考=松居桃樓論
第9章 書評=三者三論
第10章 “ほほえみ”の章
松居桃楼と言っても知らない人が多いでしょうが、「アリの街のマリア」や「ゼノ死ぬひまない」の著者です。1994年に逝去していますが、この時代にあってこそ松居桃楼の思想を掘り起こすべきと考えます。
この本は松居桃楼の生涯の同志であった田所静枝氏の遺した文章も掲載されており、松居桃楼を研究するための貴重な資料ともなることでしょう。
まさに天才であり、博覧強記であった松居桃楼をふたたび世に紹介してくれたこの本を感謝とともに紹介します。

シオン賢者の議定書
ダイナミックセラーズ出版 1986年版
シオン賢者の議定書関連はいくつか出版されているが、決定版ともいえる読み安さ。こちらも絶版本となり、現在はアマゾンで5000円前後で中古本が売られている。
松居桃楼さんのトルストイの予言で、「4 世界征服を狙う怪文書」の章で陰謀論を取り上げている。
一度、桃楼おじいさんに陰謀論についての評価を伺ってみたことがある。「あなたがた(若い人たちという意味)のやろうとしていることに比べたら、陰謀論など屁みたいなものだ」と一喝された。
真理を追究する慧眼の前には、陰謀論は、ただの屁でしかなかった(笑)
ダークサイドに取り込まれることなく、一度読んでおくことは、けっして無駄ではない。ヒトラーが牢獄時代に書いた「我が闘争(マイネカンプ)」の火つけ役になった原典の書だ。読むことには歴史的意義がある。
ダイナミックセラーズ出版にいらした高田さん、お元気かな。

こち亀 194巻
集英社 2015年03月出版
「霧の中のアリア」というタイトルで
秋本治先生が、全201巻、全1960話中で唯一「蟻の街のマリア」に関する内容を描かれている。
東京都からの立ち退き要求で、廃品回収の出来ない都心から遠く離れた8号埋立地を代替地としてあてがわれたことで
商売が成り立たなくなった経緯、問題の本質が分かりやすく暴かれている。
現在は電子書籍化が進んで、この作品も簡単に閲覧できる。現在紙の本は550円、電子書籍は522円で、割安感はほとんどないので、腹立たしい限りだが、それは秋本治先生のせいでも集英社のせいでもない。
集英社にいらした、角南攻元編集長、世良光弘さん(現在は軍事評論家としてご活躍中)、お元気ですか?

横田南嶺
春秋社 2020年08月出版
横田南嶺(よこた・なんれい)
臨済宗円覚寺派 管長
1964年和歌山県新宮市生まれ。87年筑波大卒。大学在学中に出家得度し、卒業と同時に京都の建仁寺僧堂で修行。91年から円覚寺僧堂で修行し、99年に円覚寺僧堂師家。2010年に臨済宗円覚寺派の管長に就任した。
著作多数。日本で最も多くSNSを活用して発信している僧侶のひとり
私より若いのに、声が渋く話が深い(^^;)
松居桃楼氏に関するお話をホームページやYouTubeなどで数々発信されています。
以下YouTubeより引用
「私と『天台小止観』との出会いは、昭和五十三年にさかのぼります。 私がまだ十四歳の頃であります。 NHKラジオ宗教の時間で、松居桃楼(とうる)先生が講義されたのでした。 毎月一回で、十二回にわたっての講義でした。 その十二回の講義が、一冊の本になっています。 一九七九年に、『禅の源流をたずねてー天台小止観講話』として柏樹社から刊行され、その後、潮文社から『微笑む禅 生きる奥義をたずねて』と題して新たに出版されています。 今はもう入手困難な本であります。 松居先生の語り口が穏やかで、実にご丁寧であったことを覚えています。 松居先生は、幼少の頃から、死の問題について考え悩まれていたそうです・・・」